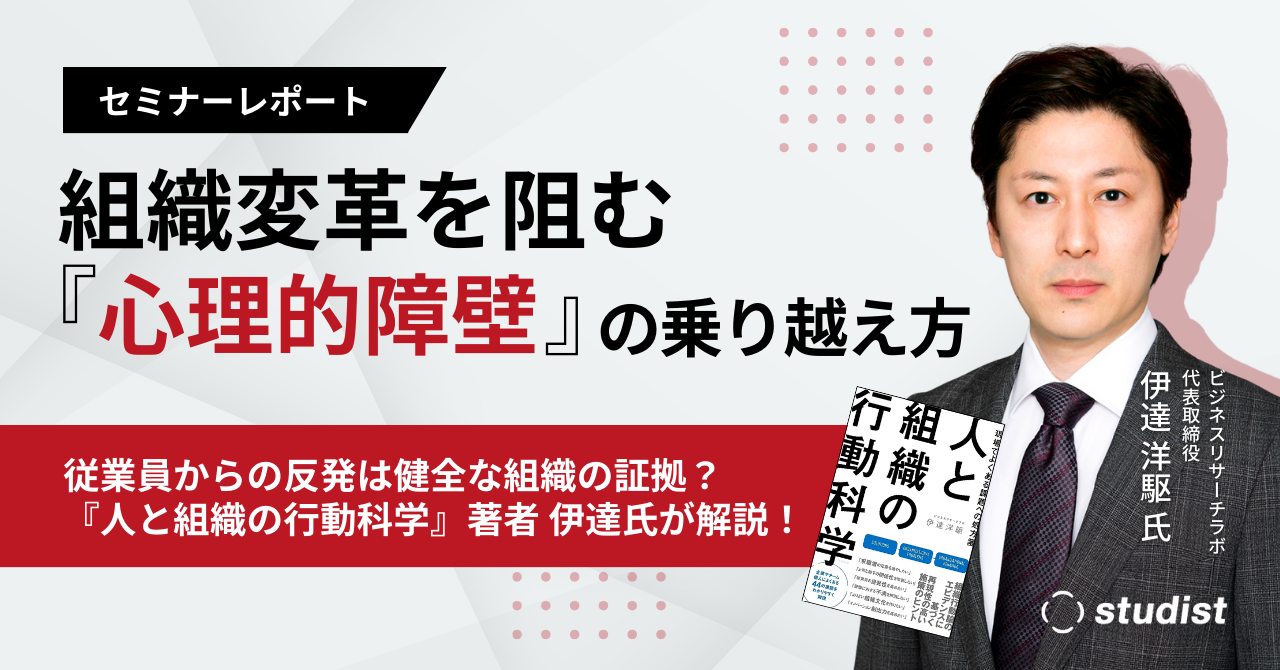
弊社スタディストが、組織変革を目指す経営者/リーダーの皆様向けに開催したオンラインイベント『組織変革を阻む心理的障壁の乗り越え方』にて、株式会社ビジネスリサーチラボの代表取締役 伊達洋駆さんに講演いただきました。
伊達さんは、組織サーベイや社内データ分析のプロフェッショナルであり、人材育成や組織行動論などについて複数の書籍も出版されています。
組織変革において「従業員の反発によって変革が進まない」というのはよく聞く話です。しかし、なぜこのような反発が起こるのか、従業員がどのような感情を抱いているのかを、体系化して研究・分析したという企業は少ないのではないでしょうか。
本記事では、伊達さんの講演内容をサマリーとしてお届けします。
人事領域における組織サーベイや社内データ分析のプロフェッショナル
ビジネスリサーチラボ 伊達さん(以下、伊達):ビジネスリサーチラボの代表取締役を務める、伊達と申します。
神戸大学大学院経営学研究科で研究者としてのキャリアを歩む途中で、ビジネスリサーチラボという会社を立ち上げ、現在に至っています。ビジネスリサーチラボは、人事の領域において、組織サーベイや社内データ分析などのサービスを提供している会社です。
本日は『組織変革を阻む心理的障壁の乗り越え方』というテーマで講演させていただきます。
組織変革において心理的障壁はなぜ生じるのか
伊達:では最初に、『心理的障壁が生じる理由』についてお話します。
みなさん、組織を変えようとしたときに従業員から反発に遭ったり、スルーされたり、ネガティブな感情をぶつけられたりした経験はないでしょうか?この現象の背後には、従業員の『心理的障壁』があります。
実はここに、組織の興味深い原理があるんです。まずはその原理についてお話ししたいと思います。
組織は学習し、ルーティン化をおこなう
伊達:組織は、市場環境における生き残りをかけて試行錯誤し、さまざまな取り組みをおこないます。その試行錯誤のなかには、うまくいくものもあれば、そうでないものもあります。それを経て、成功したものを残し、失敗したものを棄却していくのです。
このように組織が学んでいくプロセスは、専門的な言葉では『組織学習』と呼ばれ、どのようなステップをたどるのかが整理されています。
- ステップ1 情報獲得:組織が情報を得る
- ステップ2 情報分配:組織内で情報を共有する
- ステップ3 情報解釈:組織内で情報を読み解く
- ステップ4 組織記憶:組織としての記憶になって定着する
この4つの流れは、企業の規模を問わず、ベンチャーでも大企業でも進められています。
伊達:組織学習のゴールとして、次に同じ課題が現れたときにうまく適用できるよう、ルーティン化が起こります。
このルーティン化は、組織にとって非常に大事です。なぜならルーティンができあがってしまえば、組織は環境に対して安定的に対応し、成果を上げていけるようになるからです。
これまでのルーティンから外れる=不確実性の高い状態となることが心理的障壁を生む
伊達:組織変革は、ここまで説明した組織学習の成果、つまり今までの試行錯誤や、その結実であるルーティンに対する「挑戦」であるといえます。
少し想像していただきたいのですが、今まで組織で当たり前に進められてきたルーティンを、いきなり「今からは使えません、別の方法をとってください」と言われたらどうでしょうか?あまりいい思いはしないですよね。
従業員にとっては、「今までの方法が通用しなくなる」という感覚に苛まれ、「これまで築き上げてきたものが無に帰す」という気持ちになり得るということです。
なぜそんな気持ちになるのかというと、人は今まで自分が慣れ親しんだ方法を変えるときに、情報不足に襲われます。新しい方法に対して、「どうすればうまくいくのか」「そもそも何をするのか」といった情報を、十分に持っていない状態になります。いわば未知の世界です。
そうした情報不足の状態を『不確実性が高い』と言います。
この不確実性というのは、人にとってなかなか厄介な存在です。
なぜなら、不確実性が高い状態はストレスフルだからです。組織を変えようとしたときに人は不確実性に襲われ、ストレスを感じ、その結果としてネガティブな気持ちになる。
これが、組織変革を起こそうとしたときに従業員から反発が起こる、すなわち心理的障壁が生まれるメカニズムです。
心理的障壁に直面するのは必ずしも悪いことではない
伊達:組織変革においてネガティブな感情が起こり、心理的障壁に直面するというのは、見方を少し変えると、これまで組織がきちんと学習してきたからこそだといえます。
ルーティンをきちんと作ってきたからこそ、そのルーティンが変えられることに対して不確実性が高まり、反発や無視などのネガティブな反応が起きるのです。
さらに、こんな興味深い研究もあります。「組織に対して愛着を持っている人ほど、変化に抵抗する」というものです。
組織に愛着がある人ほど、現在の組織が好きなんですね。組織に対する愛着は、専門的には『組織コミットメント』と呼ばれ、実務的には『従業員エンゲージメント』という呼び方もされます。
エンゲージメントが高い人材ほど、今の組織が好きだからこそ、副作用として「現状を維持したい」という気持ちが生まれ、変化に抵抗します。
伊達:逆に言えば、組織を変革しようとしたときに、従業員から反発も無視もネガティブな感情も何も起きないのは、あまり良い状態とはいえないわけです。
組織学習の結果として成功パターンを作れてこなかったか、現在の会社に対して愛着を持っていないかもしれないからです。
組織変革の際に心理的障壁が生まれるのは、ある意味で組織がうまくいっていたから、と考えられます。
反発や無視などの反応があったときは、ポジティブに「今までがきちんと機能していたからだ、よかった」と安心し、逆に反発が起きなかったときは「うちの会社大丈夫かな」と心配するくらいでいいと思います。
障壁を乗り越える「6つのポイント」とは
伊達:ここまで、心理的障壁が起こるのは自然なことであり、組織がきちんと機能している証拠だというお話をさせていただきました。
とはいえ、実際問題として、組織変革を進めるためには、心理的障壁を乗り越える必要があります。
ここからは、従業員の心理的障壁を乗り越えていくための6つのポイントをご紹介します。ポイントは以下の通りです。
① 範囲を絞る
② 行動を変える
③ 上から変わる
④ 時間をかける
⑤ 感情に寄り添う
⑥ 目的を伝える
① 範囲を絞る
伊達:1つ目が、「範囲を絞る」です。
先ほどご説明したとおり、組織を変えるということは、従業員を不確実性に直面させ、不慣れな方法へと向けていくことになります。そのため、大きな変化を起こそうとすればするほど、従業員は大きな不確実性にさらされ、心理的障壁も大きくなります。
そこで有効なのが、変革の範囲をできるだけ絞ることです。
営業でたとえてみます。これまでうまくいっていたプル型の営業から、今後はプッシュ型の営業に切り替えていこう、となった場合。
突然プル型の営業をすべて撤廃し、プッシュ型営業に完全に入れ替えようとするのは、非常に大きな変革ですよね。これでは不確実性も大きくなるため、心理的障壁も大きくなり、進めにくいです。
そこで、最初は変革の範囲を限定します。
突然プッシュ型営業に完全に切り替えるのではなく、例えば、まずはクライアント向けの自社セミナーを開催したら、セミナー参加者に連絡することから始める。
このように、大きな変化ではなく小さなステップから始めるという考え方が、組織変革においては重要です。
小さな変化でも積み重ねていけば、変わることに対して従業員が自信を持つようになり、慣れによって「変わっていけそう」という気持ちが芽生えます。そうなったら、変化の範囲を少しずつ広げ、より深いレベルの変化に進んでいくのがいいでしょう。
② 行動を変える
伊達:2つ目が、「行動を変えるように仕向けていく」です。
新しい環境に人が慣れていくプロセスの研究で、「人は意識から変わるのではなく、行動から変わっていく」という結果が明らかにされています。
組織を変えるときも、マインドから変えようとするとなかなかうまくいきません。変革のターゲットとして、まずは行動を変えるようにするのが有効です。
先ほどの、プル型の営業をプッシュ型に変えるという例で再びお話しすると、「プル型営業の『相談を待つ』という姿勢がいけない、マインドを変えていこう」という考え方から入ると、変革が難しくなります。そうではなく、行動から変えていくのです。
「これまではセミナー参加者に対してアクションを起こしていなかったので、今後はセミナー開催から1営業日以内に連絡するよう徹底していきましょう」というふうに、具体的な行動に落とし込んでいくのが大切です。
伊達:変革のターゲットを「行動」に置くメリットとして、行動は観察できるという点もあります。
狙った行動がちゃんと起きているのかどうかをチェックできるのです。これは、変革を確実に進めるうえでのメリットになります。
③ 上から変わる
伊達:3つ目は、「上から変わる」です。
組織変革でよく言われることとして、「組織変革を呼び掛けたが、上が変わらないので、従業員も冷めてしまう」というのがあります。
組織変革を進めるには、まずは役職者から率先して自分の行動を変えていきましょう。
具体的には、まず経営者やマネージャーに行動の変容を求め、行動が変わった姿を従業員に見せていきます。
あるいは、組織変革を推進している部から率先して変えていき、「自分たちはこう変わりました」という見本を示す。
上の人が率先して変化を見せていけば、従業員も「自分も変化しないと駄目なんだな」と思えるわけです。
④ 時間をかける
伊達:4つ目は、「時間をかける」です。
人はそんなにすぐに変われるものではない、という点を押さえておいてください。
大きな変化を起こそうとしたときに「はいわかりました、明日からすべて変えます」とはなれないんです。変革には時間がかかるということを認識しておき、腰を据えてじっくり進めていく必要があるのです。
また、一度変化を呼びかけただけでいきなり変わる、というのも困難です。何度も何度も繰り返して伝えていく必要があることも、織り込んでおかなければなりません。
⑤ 感情に寄り添う
伊達:5つ目が、「感情に寄り添う」です。
組織変革を進めていくときに重要なことは、大きく以下の2つになります。
- 変革を進めること=課題志向
- 感情に寄り添うこと=関係志向
先ほど申し上げたとおり、組織変革を進める際に、従業員がネガティブな感情を抱くのは当然で、組織がうまくいっていた証拠でもあります。
ただし、ネガティブな感情も歓迎だからといってそれを放置してしまうと、心理的障壁を乗り越えられなくなってしまいます。
重要なのは、変革を進めると同時に、従業員の感情にも寄り添うこと。そのために、従業員との関係性を普段から作っていきましょう。
この「変革を推進する担当」と「感情に寄り添う担当」は、1人で両方とも進めるのは困難な場合もあります。そのときは、役割を分担してください。
組織変革の際には、変革を進める人だけでなく、感情に寄り添う役割の人も作っておくようにしましょう。
⑥ 目的を伝える
伊達:最後の6つ目が「目的を伝える」です。
同じ変革をおこなうにしても、なぜ変革をおこなうのかといった目的によって、従業員の受け止め方が違います。
具体的には、「自分たちのことを考えて変革をしようとしてくれている」と従業員が認識すると、変革に対して前向きになりやすいですよね。
逆に、「自分たちを搾取するために変革しようとしている」と思われてしまうと、変革は進みにくくなり、心理的障壁がより強固になります。
「自分たちのために変革してくれようとしている」と従業員に認識してもらうため、目的を伝えていく必要があるわけです。
例えばプル型・プッシュ型の営業を例にとると、「プル型からプッシュ型の営業に変えることによって、顧客との接点が増え、顧客に対しての提供価値を高められます。すると、自然と利益も高まるので、高めた利益を従業員に還元したいのです」と伝える、などがあり得ます。
従業員に対して「なぜこれをおこなうのか」と「それによるメリット」を提示し、「みなさんのことを考えての変革です」と伝えていきましょう。
伊達:最後に内容をおさらいします。
組織を変えようとすると、最初のうちは心理的障壁に直面します。
心理的障壁は組織がうまく機能してきた証拠なので、必ずしも悪いものではありません。
とはいえ、そのまま放置していては組織変革が難しいため、ご紹介した6つのポイントを押さえて、心理的障壁を乗り越えていってください。
質疑応答
現場の変化を促すおすすめの方法は?
伊達:「現場だけに変わってもらおうとする」のではなく「現場と一緒に変わっていく」という姿勢を見せることが重要です。
他人事のような姿勢で働きかけられても、人は変わろうとしません。
まずは、変革を進める側が自ら変わろうとしている様子を現場に見せてください。「自分も変わるので、皆さんも一緒に変わっていきましょう」というアプローチです。
「現状を変えたくない」という従業員は、単に楽をしたいだけなのでは?
伊達:おっしゃる側面もありますが、人は誰しも苦労をしたくないものです。
組織としても、学習の成果としてのルーティンを踏襲するほうが安定しているため、変わりたくないと思うのです。
そのことを念頭に置いたうえで、変化を拒む人たちには共感を持って接してみてください。変革が前に進みやすくなります。
会社のための変革でも、自部署にメリットが感じられないと賛同されない...。
伊達:これは「愛着」がヒントになります。従業員は、自分の部署に対しては愛着を持っているが、会社全体に対しての愛着は持てていないというパターンがあります。
普段から、会社が従業員個人に対して「あなたたちのことを考えています」という支援と発信をしていなければ、従業員個人が会社全体のメリットを優先するのは難しいでしょう。
会社として従業員への支援を意識的におこない、さらに、それが従業員に伝わるよう心がけましょう。
マネージャーや経営層の意識を変えるために現場側からとるべきアプローチは?
伊達:これまで様々な企業を見てきましたが、論理的な説得だけで経営層が変わった例は多くありません。
そこでおすすめなのが、実際に変化に成功している社員や部署と関わってもらうという方法です。
経営層は、そのような社員と繰り返し会話することで実例を情緒豊かに知り、変革に対してポジティブな感情を抱くようになっていきます。
「社員発案の変革を経営層が否定する」が繰り返され、社員が変革に心理的障壁を抱いている...。
伊達:この問題には、ふたつの論点があります。
1つ目は、「なぜ経営層が現場からの変革に反発するのか?」です。
ここまでお話しした心理的障壁の原理は、経営層にも当てはまります。
経営層もこれまでの学習によって現在のルーティンを獲得してきています。そのため、それを突き崩すような変革に抵抗してしまいます。これも、経営層が学習してきた結果です。
2つ目は、否定を繰り返されたことによる「どうせ言っても無駄だ」という従業員の諦めです。これを「学習性無力感」といいます。
従業員が学習性無力感に陥ってしまったときは、まず現場で小さい成功例を積み重ね、それを現場内で情報交換して普及させていくというやり方をとってください。
現場で普及した成功例を持って経営層へアプローチしていくことで、変革に対する理解が得られやすくなります。
上司が「組織変革を進めよう」と言いつつも行動には移さない。部下の行動も変化しない...。
伊達:その上司自身が、変革に対して心理的障壁を抱いているからでしょう。
その方も経営層から「変革が必要だ」と迫られているものの、これまでの学習の成果を変えたくないという状況が考えられます。
このときに有効なのは、部下側から上司への「一緒に変わりましょう」という提案です。
どんな立場であっても、相手に求める前に自分から変わり、巻き込んでいく姿勢が必要です。
さらに、チームで定例会を開催し、メンバーそれぞれが「何を変えるのか」「どう変わったのか」を共有する方法もおすすめです。このような場があることで、上司は「自分も変わらなければ」と感じるようになるでしょう。
市場変化に対応するため業務変革が急務。従業員に危機感を感じてもらうには?
伊達:まず知っていただきたいのは、ホラーストーリーは人を動かしにくいということです。
「今のやり方を続けると悪い結果になります」と、悲劇的な結末を仄めかす語り方を「ホラーストーリー」というのですが、ホラーストーリーで人はなかなか動きません。
むしろ、明るい未来を従業員に伝えるのがおすすめです。
「変革をおこなえば、こんなにいい未来が待っています」ということを、なるべく具体的に伝えてください。
さらに、少しでも変化に成功している個人や部署があれば紹介します。従業員が将来像を具体的に描けるようになり、結果として組織全体での変革が前進します。
組織変革の課題をどう解決していくかだけでなく、組織学習の仕組みや人間の心理について、詳しく解説いただきました。今回の内容が、みなさまの次のアクションに繋がることを願っております。